
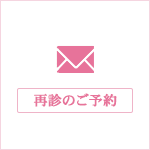

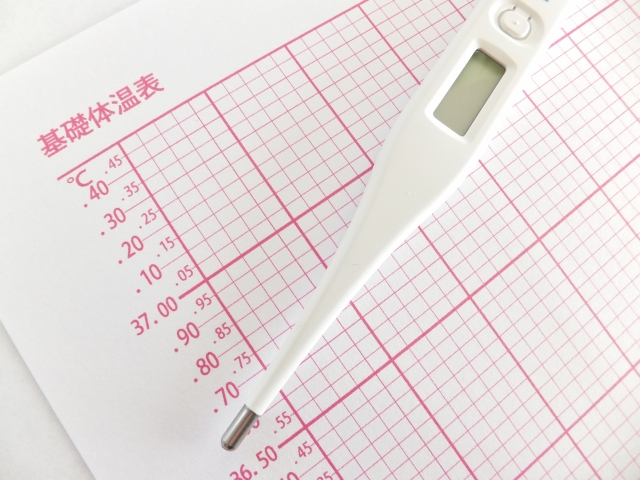
妊娠を望んでいる方の中には、「排卵日はいつ?」「タイミングは合っているのかな?」と悩む方が少なくありません。排卵のタイミングを知ることは、自然妊娠を目指すうえでも、不妊治療を始める際にも大切な“第一歩”です。
今回は、排卵日を正しく予測するための基本知識として、「基礎体温」と「排卵検査薬」の活用法について解説します。
排卵とは、卵巣から卵子が排出される現象のこと。一般的には生理開始から約14日目前後に排卵が起こるとされていますが、周期や体調によって前後することもあり、自分の排卵日を正確に知るにはセルフチェックが必要です。
排卵日前の1〜3日までが「妊娠しやすい時期」とされており、タイミングを取るうえで重要な情報となります。
基礎体温とは、朝目覚めてすぐ、身体を動かす前の体温のこと。毎日記録することで、排卵の有無やタイミング、ホルモンバランスの傾向が見えてきます。
基本的なパターン(例)
低温期(生理後〜排卵前):36.0〜36.4℃前後
排卵期:体温が一時的に下がることがある
高温期(排卵後〜生理前):36.7℃前後に上昇
一般的に低温期から高温期になると体温が0.3-0.5度程度上昇します。
高温期が安定して2週間続いた後に体温が下がれば生理が来たサイン、継続して高温が続けば妊娠の可能性も考えられます。
排卵検査薬は、尿中の**LH(黄体形成ホルモン)**の急上昇を検出することで、排卵の“直前”を予測できるツールです。
生理周期が安定している方は、次回生理予定日の約17日前から検査開始
毎日同じ時間帯(朝または夜)に採尿して検査
陽性反応が出た翌日〜翌々日が排卵の可能性が高い
排卵日の直前を把握しやすい
客観的な数値で判断できる
多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)の方は陽性が続く場合も
排卵が必ず起こるとは限らない
「陽性=排卵済み」ではない:あくまで排卵“予測”であり、排卵後に検査しても陽性になることがあるため、タイミングの取り方に注意。
基礎体温がガタガタでも問題なし?:多少の変動はOK。ただし2層性(低温期と高温期の分かれ目)がない場合は医師への相談をおすすめします。
どちらか一方だけでは不十分なことも:基礎体温+排卵検査薬を併用することで、より精度の高い予測が可能に。
生理周期がバラバラ
排卵がない(無排卵)月がある
基礎体温が常に低い or 高温期が短い
検査薬の反応が曖昧
こうした場合は、ホルモン検査や超音波による排卵チェックが有効です。クリニックでの検査により、排卵の有無や卵胞の成長状況を正確に把握することができます。
ファティリティクリニック東京では、高度な医療と、心に寄り添うサポート体制の両立を目指しています。以下の3つの方針に基づき、安心して治療に取り組んでいただける環境を整えています。
① 医療の安全管理
ISO9001の認証を取得し、医療安全管理室を設置。卵巣過剰刺激症候群(OHSS)や多胎妊娠のリスク回避、災害時でも培養機器が安定稼働するようなシステムを導入しています。
② 高い医療水準の維持
JISART(日本生殖補助医療標準化機関)の監査合格施設として、精密な胚培養技術と専門スタッフによる治療体制を確立。単一胚移植による高い妊娠率の維持を目標に掲げています。
③ 心に寄り添う医療の実践
医師・看護師・胚培養士・心理カウンセラーが連携し、検査や治療の内容を一つひとつ丁寧にご説明します。不妊治療が「つらいもの」ではなく、「希望に向かう選択」として感じられるようサポートします。
今回は、排卵日予測の基本として「基礎体温」と「排卵検査薬」の活用法について解説しました。
排卵日を正しく知ることは、妊娠に向けた最初の一歩。ご自身の身体のサイクルを知ることで、自然妊娠を目指す方にとっても、不妊治療のスタートを考えている方にとっても、大切なヒントになります。
「うまくいかない」「測っているけどよく分からない」という場合でも、必要以上に落ち込まず、どうぞ一度ご相談ください。
ファティリティクリニック東京では、排卵の診断やタイミング指導から専門的な治療まで、お一人おひとりに寄り添いながらご提案いたします。