
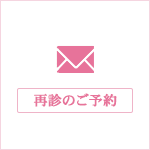


不妊治療を始める前に、いくつかの検査を行い原因を探ります。医師の指示により、月経の周期に合わせて行います。
1) 月経中(月経1-5日)
2) 排卵前(月経終了後)
3) 排卵時(月経12-14日頃)
4) 黄体期(高温相5-7日頃)
5) 月経の時期に関係なく行う検査
6) その他
LH/FSH/PRL/E2測定
卵巣の機能を調べるための血液検査です。
LH-RHテスト/TRHテスト
月経が不順である場合、その原因がどこにあるのかを明らかにする必要があります。
LH-RH テスト・TRHテストはLH-RH又はTRHという注射を行い、注射前、注射後30分、60分に採血をし、それぞれホルモンを測定することにより月経異常が排卵に関わるどの部分によって生じているのかを明らかにする検査です。
検査当日、食事制限はありません。
子宮卵管造影
卵管が詰まっていないかどうかを調べる検査です。シリコン製の柔らかく細いカテーテルを用いて子宮内に造影剤を注入し、子宮の形、卵管の通過性を確認します。この検査は痛いと心配される方もおられますが、痛みの少ない方法で行いますので心配ありません。この検査を排卵前に行う理由は、妊娠している場合にこの検査が妊娠に影響を及ぼす可能性があるからです。月経から検査終了まで避妊してください。
超音波検査
排卵が近づくと子宮内膜は厚くなり、卵子を包む卵胞は直径約2センチにまで発育します。これらの変化を超音波で確認します。
フーナーテスト
精子と頚管粘液の適合性を調べる検査です。頚管粘液が充分に分泌されている排卵の時期に性交渉を行い、当日もしくは翌日に来院していただき、頚管粘液中の精子を調べます。
※未入籍や、身分証の変更がお済でない方、外国籍の方は指定の書類が揃い次第行います。
超音波検査、黄体ホルモン検査
排卵後に黄体ホルモンが分泌され、子宮内膜を厚くして受精卵を育てる環境が作られます。この時期には黄体ホルモン値を測定するとともに超音波検査により子宮内膜の厚みを調べます。
また、不妊症の原因となる異常のひとつに黄体化未破裂卵胞症候群(lutenized Unruptured Follicle Syndrome;LUF)があります。この異常があると卵子が卵巣内にとどまり、外に飛び出す事が出来ません。この時期に超音波をすることによりLUFの有無についても調べます。
初診スクリーニング検査
お手持ちのデータがある場合でも、スクリーニング検査は一律に行います。
検査項目は治療内容や医師の診察によりますが、以下のような検査を行います。
・HIV抗原・抗体
・HBs抗原
・HCV抗体
・梅毒(RPR・TP抗体)
・クラミジアトラコマティスIgG・IgA・DNA
・風疹ウイルス抗体
・甲状腺(TSH/FT4)
・その他(健康状態等)
AMH(Anti-mullerian Hormone:抗ミュラー管ホルモン)
AMH(Anti-mullerian Hormone:抗ミュラー管ホルモン)とは、発育過程にある卵胞から分泌されるホルモンで、女性の卵巣予備能を知る指標になると考えられています。
女性の卵巣の中には、生まれつきたくさんの原始卵胞があり、初経の頃より原始卵胞が活発化し、発育卵胞→前胞状卵胞→胞状卵胞→熟成卵胞と成熟し、約190日かけて排卵します。
AMHは前胞状卵胞から分泌され、その測定値と発育卵胞の数は相関します。従って、AMH濃度を測定することによって、残存する卵胞の数を測定し、卵巣予備能がどれくらいか推定することができます。
また、多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)ではAMH は高値を示すことがあります。
卵巣内の発育卵胞数を知ることによって適切な排卵誘発法を選択することができるため、逆に卵胞が育ちすぎて卵巣が腫れてしまう卵巣過剰刺激症候群(OHSS)のリスクを下げることができ、効率良く治療を進めることができます。
CA125の検査(但し月経中以外の時期)
CA125は子宮内膜症のときに上昇する物質で、これを測定することにより子宮内膜症の有無を推定する事が出来ます。CA125の測定は血液検査で行いますが、月経中は数値が本来より高めに出るため、月経時を避けて検査を行います。また、CA125はすべての子宮内膜症で上昇するわけではなく、軽度の子宮内膜症の場合には正常値であることもあります。そのため子宮内膜症の診断は超音波検査や腹腔鏡など、他の検査の結果と総合して行う必要があります。
精液検査
習慣性流産検査
抗精子抗体
精子が体内に入る事により精子に対する抗体を作ってしまうことがあります。この抗体が強いと、精子が体内に入った途端に動かなくなってしまいます。これを免疫性不妊症といいます。この抗体は血液検査によって測定することが出来ます。